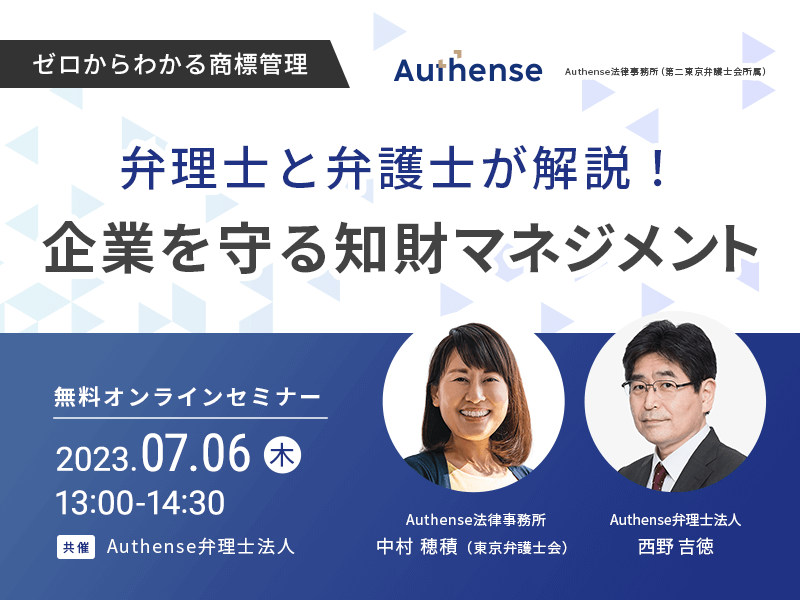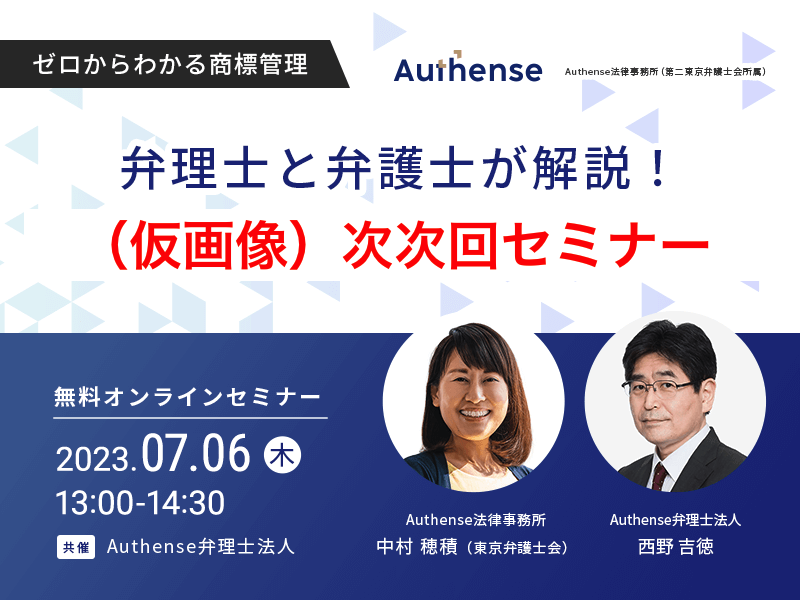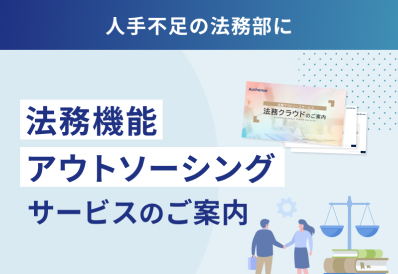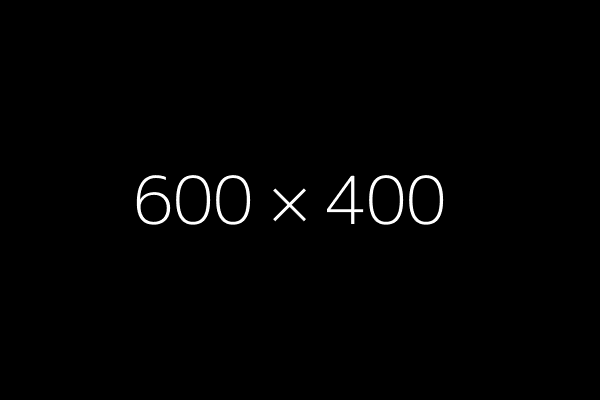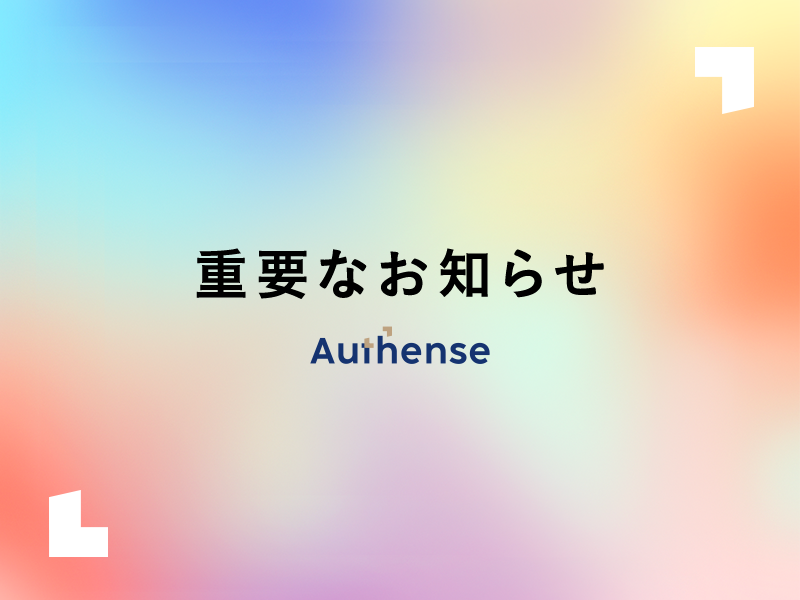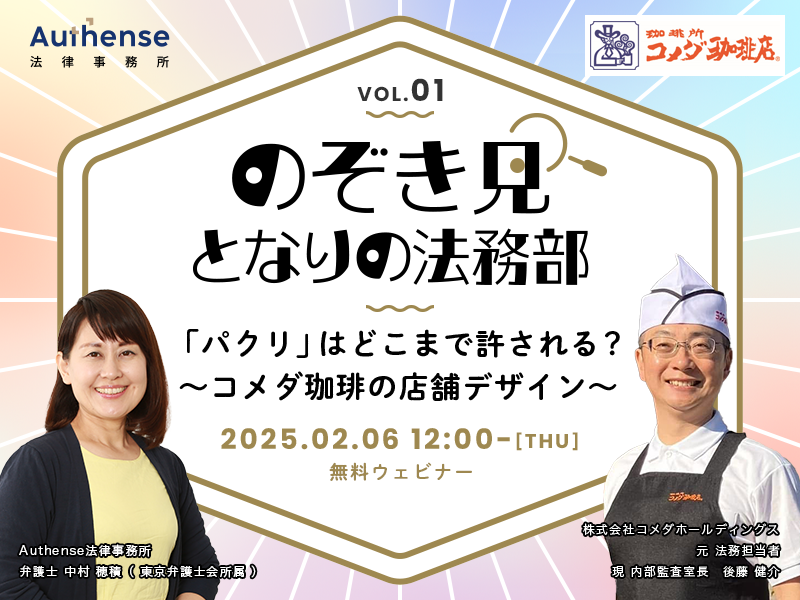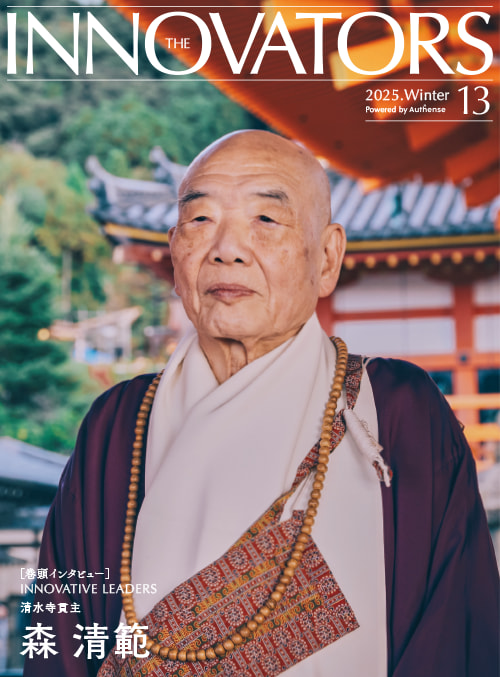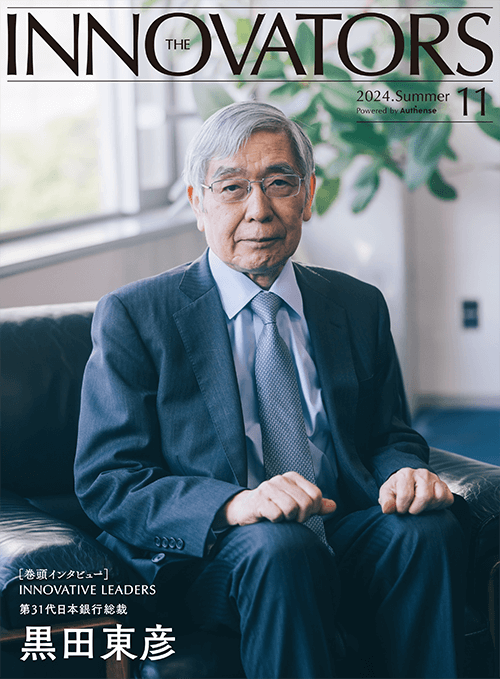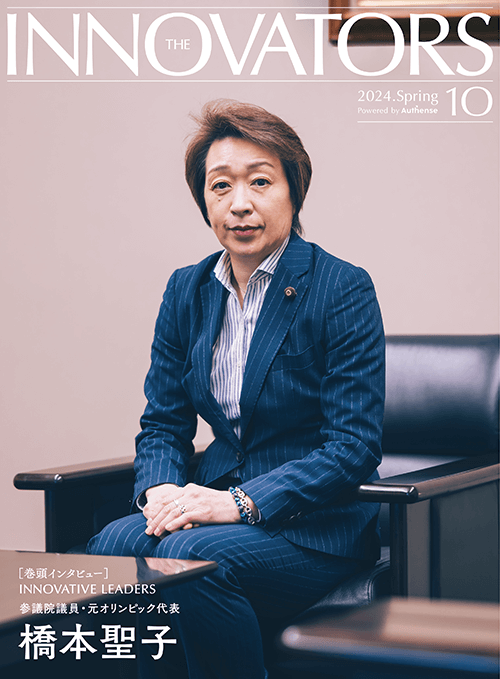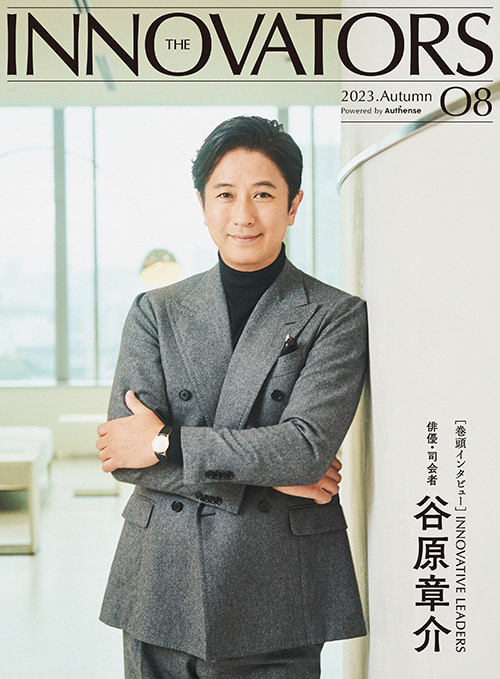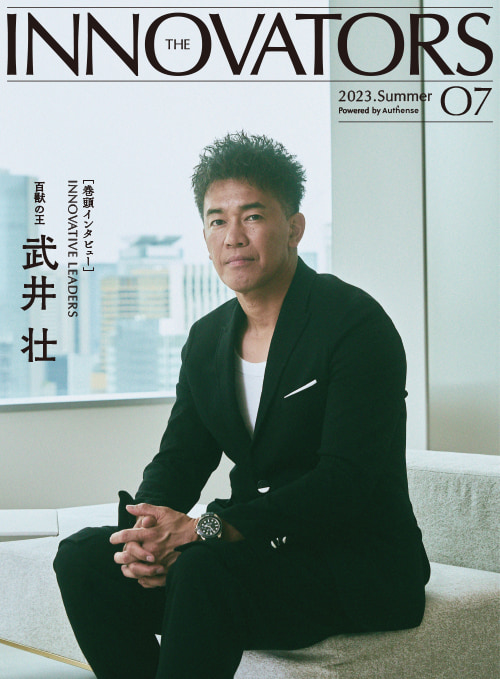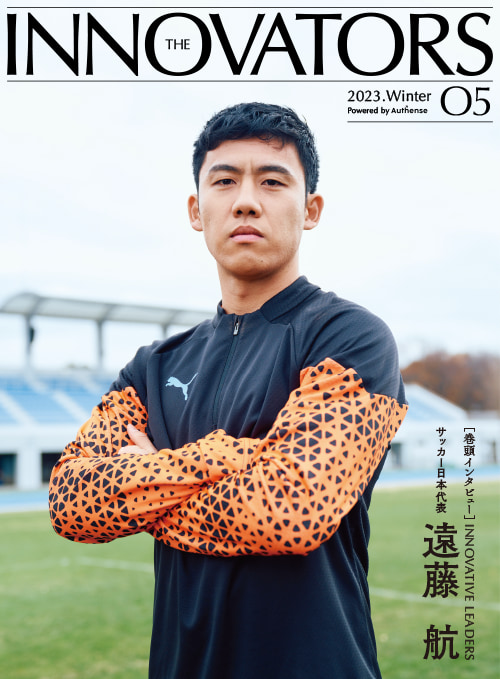企業の不祥事を抑止するためには、内部監査やモニタリングの強化が有効です。
では、企業で不祥事が起きると、どのようなリスクが生じるのでしょうか?
また、内部監査やモニタリングを弁護士に依頼することには、どのようなメリットがあるのでしょうか?
ここでは、内部監査・モニタリングの概要やこれらの目的、不祥事が企業にもたらすリスクや内部監査・モニタリングについて弁護士に依頼するメリットなどを解説します。
Authense法律事務所は企業の内部監査・モニタリング体制の構築支援について豊富な実績を有しています。
内部監査・モニタリング体制の整備や強化、内部監査システムの評価などをご希望の際は、Authense法律事務所までご相談ください。
目次

<メディア関係者の方>取材等に関するお問い合わせはこちら
<title>内部監査・モニタリングの弁護士依頼はAuthense法律事務所へお任せください
<h1>内部監査・モニタリング
内部監査・モニタリングとは
内部監査・モニタリングとは、企業の監査役など独立した監査組織が、事業や財務会計の合法性や合理性などを調査し、評価するものです。
上場企業の内部監査ではJ-SOX監査のみならず、三様監査の充実と会計監査人との連携が求められています。
なお、内部監査の対象は企業全体に及ぶため、従業員のみならず取締役などの役員も監査対象となります。
Authense法律事務所では、業種や規模にかかわらず、内部監査の方法に関する助言やサポート業務を提供しています。
また、不祥事が発生した企業に対しては、内部管理体制の整備と運用状況について第三者の客観的な評価やモニタリングを通じた助言も可能です。
内部監査・モニタリングが必要な企業
内部監査やモニタリングは、どのような企業で必要となるのでしょうか?
ここでは、これらが必要となる企業について解説します。
自社に内部監査やモニタリング体制の整備が必要か否か判断に迷う場合や、自社に合った内部監査システムを導入したい場合などには、Authense法律事務所までお気軽にご相談ください。
会社法上の大会社
内部監査は、会社法で定められた義務ではありません。
ただし、会社法上の大会社には「会計監査人」の設置が義務付けられています(会社法328条2項)。
会計監査人とは計算書類などの会計を監査する機関であり、公認会計士または監査法人だけが就任できます。
また、大会社であり、かつ公開会社である場合(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く)には監査役会と会計監査人の設置が必要です(同1項)。
監査役会を設置するには監査役が3名以上必要であり、その半数以上は社外監査役である必要があります(同335条3項)。
これらの企業は外部に及ぼす影響も大きいため、より強固な内部監査体制が求められているといえます。
なお、会社法上の大会社とは、資本金5億円以上、または負債額200億円以上の会社です(会社法第2条6項)。
取締役会設置会社
取締役会設置会社は、監査役の設置が義務付けられています(同327条2項)。
監査役とは、取締役などの業務執行を監査する機関です。
会計監査人とは異なり、資格などの制限はありません。
上場企業
上場会社は有価証券報告書を提出しなければならず、この提出義務がある企業は内部統制報告書も提出しなければなりません(金融商品取引法24条の4の4)。
この内部統制報告書の作成には、内部監査の実施が必要です。
成長発展を目指す企業
大企業や上場企業において内部監査やモニタリングが事実上の義務である一方で、これらに該当しない企業が内部監査やモニタリング体制を整備できないわけではありません。
むしろ、上場を目指す企業や成長発展を目指す企業は、早い段階から内部監査やモニタリング体制を整備し、不正を抑止する企業の足元を固めるとよいでしょう。
内部監査・モニタリングの意義・重要性
内部監査やモニタリングは、企業にとってどのような意義があるのでしょうか?
ここでは、これらの代表的な効果を3つ解説します。
- 企業の不祥事を抑止する
- 不祥事を早期に発見する
- 組織全体の向上につながる
企業の不祥事を抑止する
最大の意義は、企業不祥事の抑止です。
内部監査やモニタリング体制が構築されていないと、社内で不祥事が生じるおそれが高くなります。
不祥事には、たとえば会計不正や品質不正、横領などが挙げられます。
内部監査やモニタリング体制を整備することで不祥事が発覚しやすくなることから、不祥事の抑止につながります。
不祥事を早期に発見する
2つ目は、不祥事の早期発見です。
万が一不祥事が発生した際にも、内部監査やモニタリングを徹底することで早期に発見しやすくなります。
これにより、不祥事の早期に是正でき、影響を最小限に抑えることが可能となります。
組織全体の向上につながる
3つ目は、組織全体の向上につながることです。
内部監査やモニタリングは不正の発見だけを目指すものではなく、事業の効率化にも目を光らせるものです。
適切な内部監査・モニタリングを実施することで事業の非効率が避けられ、足場を固めつつも企業全体の向上へとつながります。
企業で不祥事が起きた場合に生じ得るリスク
企業で不祥事が起きた場合、どのような影響が生じるのでしょうか?
ここでは、内部監査やモニタリングが不十分であり企業で不祥事が起きた場合に生じ得る主なリスクを紹介します。
- 株価が低迷する・上場廃止となる
- 顧客や取引先が離反する
- 役員の責任が問われる
- 罰則が適用される
- 損害賠償請求がなされる
Authense法律事務所は企業法務に特化したチームを設けており、実際に不祥事が発生してしまった際の対応にまつわるサポートも可能です。
社内で不祥事が生じてお困りの際は、Authense法律事務所まで早期にご相談ください。
株価が低迷する・上場廃止となる
上場企業で不祥事が発生した場合、株価が低迷する可能性があります。
また、不祥事の内容が重大である場合には、上場廃止に至るおそれもあります。
顧客や取引先が離反する
不祥事が発生した場合、顧客や取引先が離反する可能性があります。
これにより、企業の収益に直接的な影響が及ぶおそれがあるでしょう。
役員の責任が問われる
不祥事の内容によっては、株主から役員の責任が問われます。
これにより、役員の辞任・解任や報酬の返上、役員から会社への損害賠償などに至る可能性があります。
罰則が適用される
不祥事の内容が法令違反に当たるものである場合、罰則が適用される可能性があります。
たとえば、必要な許認可を取得することなく業務を行っていた場合や、実際には法令でも止められる基準を満たしていないにもかかわらず満たしているとの虚偽の報告をしていた場合などがこれに該当します。
損害賠償請求がなされる
不祥事の内容によっては、不祥事によって損害を受けた相手から、企業に対して損害賠償請求がなされる可能性があります。
また、品質不正の場合に購入者から返金を求められたり、不正に操作した財務諸表を元に借入を受けた金融機関から一括弁済を求められたりする場合もあります。
弁護士に依頼できる内部監査・モニタリング
内部監査やモニタリングに関して、弁護士にはどのような業務を依頼できるのでしょうか?
ここでは、弁護士に依頼できる主なサポート内容を紹介します。
- 内部監査・モニタリング体制の構築支援
- 弁護士事務所への内部通報窓口の設置
- 内部監査システムの評価
なお、内部監査やモニタリングに関する具体的なサポート内容は事務所ごとに異なっており、どの事務所でも一律に対応できるわけではありません。
そのため、実際に依頼しようとする際は候補である事務所にまずは相談したうえで、具体的なサポート内容やサポート範囲、実績を確認するとよいでしょう。
Authense法律事務所は内部監査の方法に関する助言やサポート業務を提供しているほか、不祥事発生時におけるシステムの客観的評価やモニタリング、助言も可能です。
業種や規模に応じた適切なサポート内容を提案するため、まずはお気軽にご相談ください。
内部監査・モニタリング体制の構築支援
弁護士は、内部監査やモニタリング体制の構築支援が可能です。
企業の規模や成長ステージ、上場の有無、将来展望、業種などを加味しつつ、自社に合った的確な内部監査やモニタリング体制の構築を支援します。
弁護士事務所への内部通報窓口の設置
内部監査体制を構築するにあたって、内部通報窓口を設置することがあります。
内部通報窓口とは、従業員など企業の内部にいる人が、社内で起きている不正行為や違法行為などを相談・通報する窓口です。
2022年に施行された改正公益通報者保護法により、アルバイトなどを含む従業員数が300人超である企業には、導入が義務付けられています。
内部通報窓口を設置することで、不正の早期発見につながり、早期の是正がしやすくなります。
しかし、内部通報窓口では通報者について不利益な取り扱いをすることは禁じられており、情報の取り扱いには注意しなければなりません。
そのため、企業の内部に窓口を設置する場合もあるほか、外部の弁護士事務所を窓口とする場合もあります。
こちらも、内部監査に関して弁護士が担える役割の1つです。
内部監査システムの評価
内部監査システムを構築している場合、これが効果的に機能しているか否かを自社で判断することは容易ではありません。
特に、不祥事が発生した場合には、自社の内部監査システムの欠陥を検証する必要があるでしょう。
弁護士は、内部管理体制のシステムや運用状況について、客観的な評価や改善へ向けたアドバイスが可能です。
弁護士に内部監査・モニタリングを依頼するメリット
内部監査やモニタリングは、弁護士のサポートを受けて行うことも可能です。
また、弁護士が社外監査役などに就任し、弁護士に内部監査やモニタリングを担ってもらうこともできます。
最後に、弁護士に内部監査やモニタリングについて依頼をするメリットを解説します。
- 自社に合った内部監査体制を構築しやすくなる
- ガバナンス強化につながる
- 対外的な信用を得やすくなる
- トラブル発生時にスムーズな対処がしやすくなる
Authense法律事務所は企業の内部監査・モニタリング体制の構築や内部監査システムの評価などを行っています。
内部監査やモニタリングの強化をご希望の際は、Authense法律事務所までまずはお気軽にご相談ください。
自社に合った内部監査体制を構築しやすくなる
1つ目は、自社に合った内部監査・モニタリング体制の整備が可能となることです。
適切な内部監査やモニタリング体制は、企業の規模や業種、成長ステージなどによって異なります。
自社にそぐわない体制としてしまうと、成長速度が鈍化したり監査が行き届かず不祥事が防げなかったりする事態となりかねません。
弁護士のサポートを受けることで、自社の状況に応じた適切な体制を構築しやすくなります。
ガバナンス強化につながる
2つ目は、ガバナンスの強化につながることです。
弁護士が社外監査役に就任するなどして内部監査やモニタリングを行う場合、より厳しい目での監査が実現できます。
また、弁護士が社外監査役である場合には不祥事に対して厳格に対処されやすいことから、不祥事の抑止にもつながります。
その結果、ガバナンスの強化が可能となります。
対外的な信用を得やすくなる
3つ目は、対外的な信用を得やすくなることです、
弁護士が社外監査役などとして内部監査などに携わることは、不正を抑止しガバナンスを強化したいとの企業の姿勢を表します。
そのため、対外的な信用を得やすくなる効果が期待できます。
トラブル発生時にスムーズな対処がしやすくなる
4つ目は、トラブル発生時にスムーズな対処がしやすくなることです。
内部監査やモニタリングについて弁護士の関与を受けている場合、万が一トラブルが発生した際にも早期に弁護士へ相談しやすくなります。
そのため、的確かつスムーズな対処が可能となるでしょう。
まとめ
内部統制とモニタリングの概要やこれらのメリット、内部統制・モニタリングが不足し不祥事が生じた場合に生じ得るリスク、内部統制・モニタリングに関して弁護士にサポートを受けるメリットなどを解説しました。
内部統制やモニタリングは、企業不祥事の抑止や早期発見、企業価値の向上などを目的として行うものです。
これらが不足して不祥事が発生すると、株価の低迷や取引先の離反、損害賠償請求などの原因となります。
そのような事態を避けるため、弁護士のサポートを受けたうえで自社に合った内部統制・モニタリング体制を構築するとよいでしょう。
弁護士にサポートを依頼することで、適切な体制整備がしやすくなるほか、万が一不祥事が生じた際にも適切な対処をしやすくなります。
Authense法律事務所は企業法務に特化した専門チームを設けており、内部統制やモニタリング体制の整備についても豊富なサポート実績を有しています。
自社に合った内部統制・モニタリング体制を整備したい際や、不祥事の発生に伴い自社の内部統制システムの評価が必要な際などには、Authense法律事務所までお気軽にご相談ください。
企業規模や業種、成長段階に沿った最適なサポートを提案します。